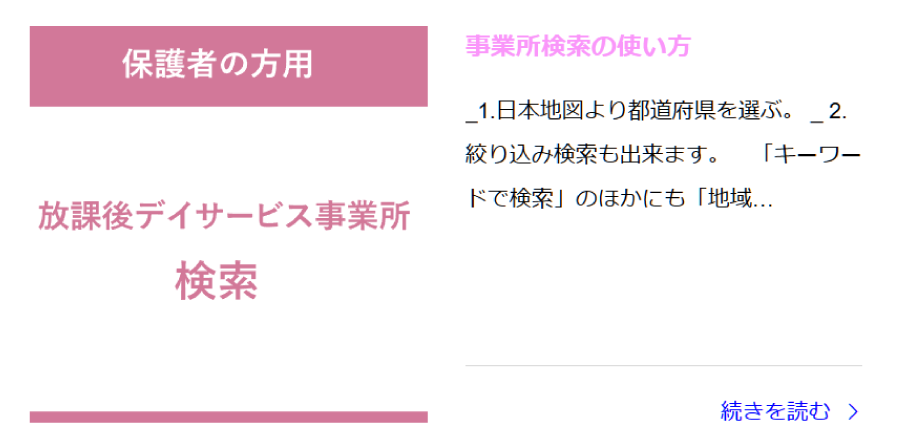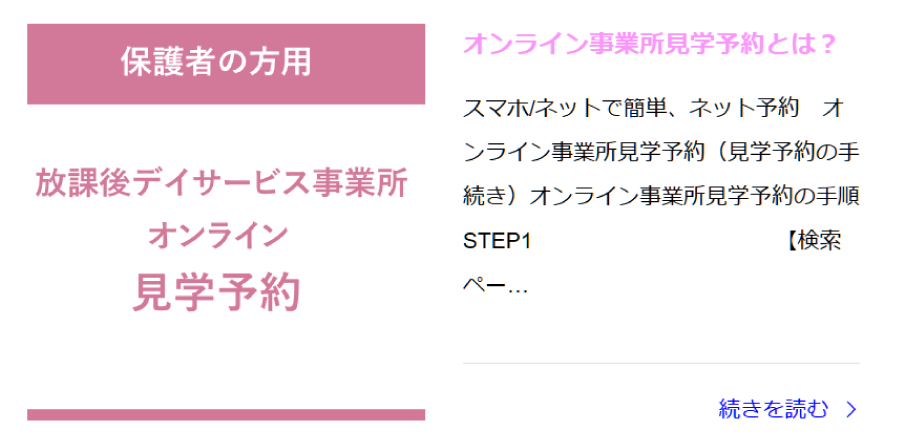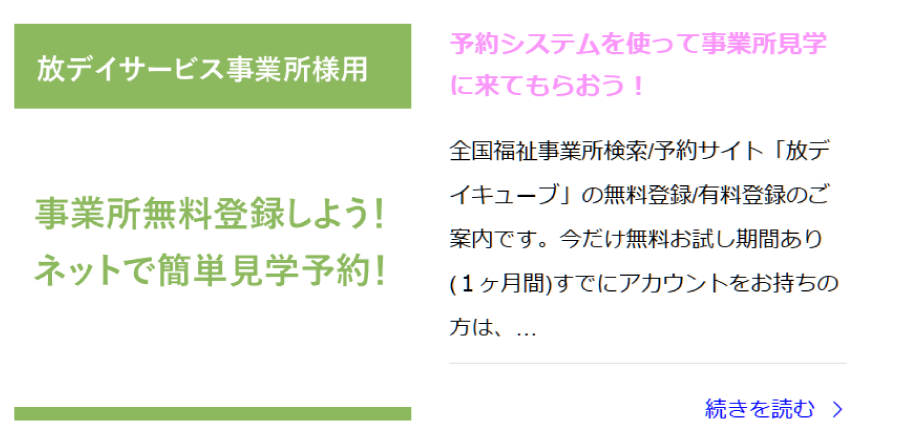回答3 放課後等デイサービスでは、それぞれが抱える障害に応じた対応を行う必要があり、利用者(児童)との関係性作りが難しくなっている現状が確かにあります。
この問題を解決するためには、知識や技術を高めるだけではなく、こどもの目線に立って支援していくことがポイントになります。発達障害のこどもは一人ひとり“こだわり”や“苦手なこと”があり、関わり方を間違えるとパニックを引き起こしたり、叩いたりすることがあります。

| 目次 |
| 発達障害のひとつADHDの児童 ▷衝動性を抑える薬物療法 ▷褒めて評価する 発達障害のひとつ自閉症スペクトラム障害 ▷「共通基盤」をつくる ▷教える側にも工夫が必要 発達障害児に必要な支援 ▷環境づくり 発達障害児への関わり方 ▷顔を見ながら穏やかに話す ▷ゆっくり、トーンを落として話す 最後に…… |
発達障害のひとつであるADHDは、不注意、多動性、衝動性が特徴だといえます。集中できなくて動き回ったり、思いついたことをその場で実行したりする傾向があります。そこで衝動性を抑えるために医者が処方箋する薬にADHDの薬物療法が採られることがあります。衝動性を抑える作用のある薬剤がそれです。水面の波が静まるように、ざわざわと揺れ動いていた気持ちが、ぴたっと静かな状態になる程に、気持ちを落ち着かせるような薬剤もあります。脳の報酬系と呼ばれる回路にはたらきかける作用があるため、脳の神経細胞の興奮の伝達に関わるドーパミンのはたらきが強まり、気持ちが穏やかになったり、頑張ろうと思えたりするようになります。
ADHDのこどもの場合、本人の行動を少しでも制御できるようにサポートすることが治療のテーマとなります。そのため、薬物療法だけでなく、こどもを褒めて評価してあげることが重要です。人はご褒美があると、それを励みにしてさらに頑張ることができるものです。ただし、「これができたら〇〇を買ってあげる」といった物との交換条件は、こどもの自尊心を育むことにはつながりません。こどもは徐々に並外れた要求をしてきて、トラブルになる可能性もあるので、「頑張ったね」「よくやったね」といった言葉による評価が大切です。では、こどものどんなところを褒めたらいいのでしょうか? 日常生活の中で、こどもの良いところを探しましょう。たとえば、いつも落ち着かないこどもでも、下の兄弟がいる場合には、兄弟の面倒を見る瞬間というものがあるはずです。ちょっかいを出していじめてばかりだったとしても、兄弟が泣いていたら、頭を撫でてあげたりすることが見られます。その時は、こどもに対して「ありがとうね!助かったよ」と心から伝えてあげたら、こどもは自らを誇らしく思います。親としては、こどもの悪いところほど気になってしまうかもしれませんが、良いところを見逃さないことが肝心です。
自閉症スペクトラム障害のこどもは、コミュニケーションをとることが苦手です。よりうまくコミュニケーションをとるためには、「共通基盤」がどれだけあるかということがポイントになります。共通基盤とは、お互いの認識の中で共通している前提部分のことです。つまり、その子の好きなことや興味のあることを理解し、それを共有することといえます。共通基盤があれば、そこからさまざまなことが相手に通じやすくなります。
学校では、こどもたちのやるべきことは常に変化していきます。基盤よりも変化のほうが多くなると、自閉症スペクトラム障害の傾向があるこどもは混乱し、苦しくなって教室を出てしまうこともあります。こういった行動を防ぐためには、教える側にも工夫が必要です。
- こどもがどれくらい授業を理解しているかよく確認すること
- 生徒が授業中にやるべきことは何なのか常に明らかにすること
- 授業1コマの中でも勉強を教えていく順序を工夫すること
などによって、発達障害の傾向があるこどもとのコミュニケーションがスムーズになることが報告されています。
発達障害の傾向は、その人の特性ですから、生涯にわたって続くものかもしれません。しかし、環境や人との関係によっては、早く不安を処理したり、健全な生活を送ったりすることができるようになります。その子にとって何が必要なのか、何をすれば明るく自信を持って生きていけるのかという点において支援をすべきだと考えます。基本的には、こどもにもっと目を向けていくことが必要です。関心が向けられているこどもは、大人の期待に応えてくれます。悪い意味での期待ではなくて良い意味で期待をする、例えば「よいことをしたね」とか「スポーツが得意だね」といったことを伝えてあげられるとよいでしょう。
こどもに適切な支援をするためには、しっかりと話を聞いて、こどもの状況を知ることが大切です。その際、こどもとどれくらい対話できるかということがポイントになります。こどもと話をするときは、できるだけ穏やかに話しましょう。赤ちゃんをあやすときのように、目と口を大きく開けてこどもを見ながら、ゆっくり、はっきりと喋ります。このように対話することで、こどもは緊張がほぐれ、いろいろなことを話してくれます。また、接する大人として、こどもに気に入ってもらえる努力をするようにしてください。少しでも気に入ってもらえれば、こどもは話をよく聞いてくれるようになります。その上で、「この2週間の学校生活を教えてね」「家でどんなことをしているか教えてね」などと質問して、こどもに沢山のことを話してもらいます。話せば話すほど自分の頭の中を整理することができるので、こどもが抱く不安を処理することにもつながります。
他者の細かな行動を観察し、リスニングにつなげる「マイクロカウンセリング」という技術があります。人は、自分が喋るスピードよりも相手のほうが早口で喋ったり、大きい声で喋ったりしたら、うまく話せなくなるものです。そのため、こどもの喋り方よりも、少しゆっくり、トーンを落として喋ることが大切です。返事をするときも、相手がしゃべり終わってからわずかに遅れるくらいがよいといわれています。こどもと対話するスキルを磨くことで、こどもたちもうまくコミュニケーションがとれるようになっていきます。発達障害のこどもと接する機会が多い方は、リスニングスキルや、マイクロカウンセリング技法を覚えると、よりスムーズに対話をすることができます。
以上のことからも判るように、具体的な行動として様々な研修を受けてみてはいかがでしょうか? 障害特性に関する知識やコミュニケーションスキルを高めることは必要なことです。また児童一人ひとりの特性や好みを把握し、対象児の目線になって、行動を理解していくことは重要なことです。さらには児童それぞれ困りごとが違うため、そのこどもにあったオーダーメイドの支援を考える必要もでてきます。長所を伸ばし、短所は補い、褒めるときは少し大げさに褒める。できないことは無理せず援助するという姿勢を保つことが、信頼関係を築くポイントとなります。