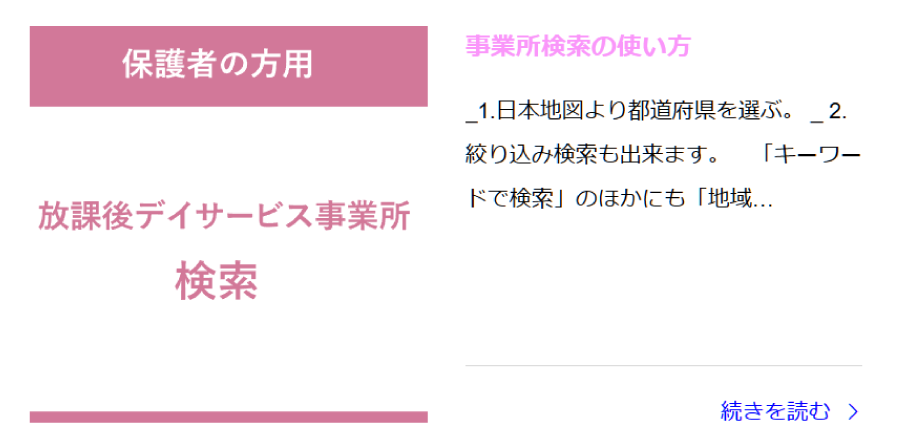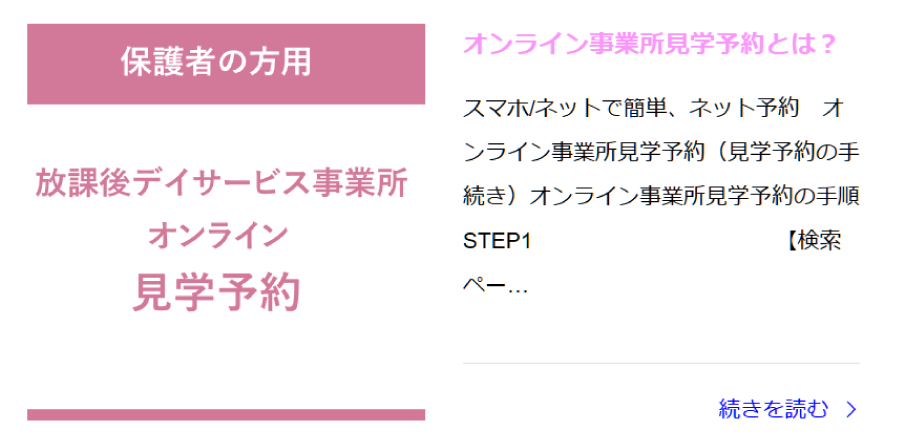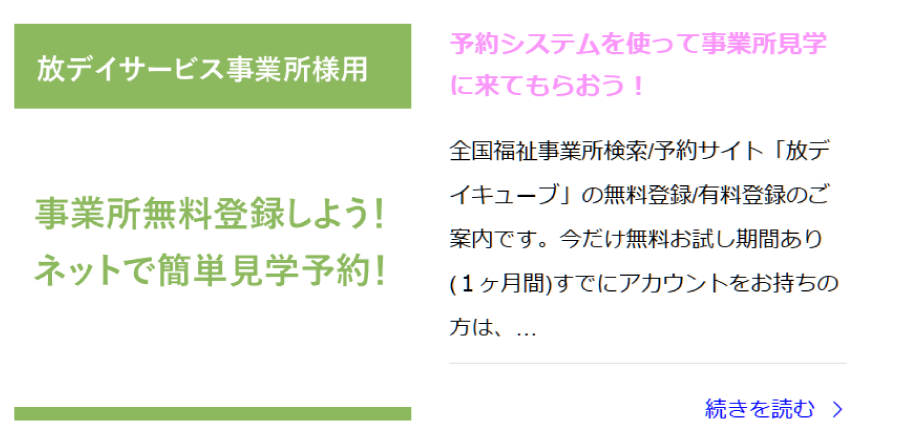| 目次 |
| はじめに…… 「指導内容が多い」という現場の悲鳴 学習指導要領と授業時間数や内容の変遷 〇授業時間数の変遷 学校教育に求められる「○○教育」の増加 グローバルな問題としてのカリキュラム・オーバーロード カリキュラム・オーバーロードの解決へ |
現在の小・中学校の教育活動は、2017年に告示された学習指導要領に基づいて実施されています(高等学校は2018年に告示)。学習指導要領は、おおむね10年に1度改訂されますので、次の告示は2027年頃となります。その改訂に向けての諸議論の中で度々登場する「カリキュラム・オーバーロード」について解説します。
学校では限られた時間で、多くのことを効率よく、かつこどもが主体的に学ぶような授業や行事などの工夫に努めています。しかし、指導すべき内容が多くなりすぎると学習者の主体性の重視は難しくなり、表面的な学びになりかねません。
指導内容が増えると教材研究や指導法の検討にかける時間も増え、教員の職務時間も超過の状態を招きます。学校の働き方改革を進めるという喫緊の課題を抱えながら、時間をかけて取り組みたいことがあるのに、時間に制限がかかるという状況に陥っています。
学校では行事や安全に関わる指導などもあるので、学校を器に例えるならば、受け入れられる内容などの量は決まっているわけですが、現在その許容量を超えてしまった状態にあると指摘され、その問題を「カリキュラム・オーバーロード(教育課程の過積載)」といわれています。
カリキュラム・オーバーロードの問題を「授業」にしぼって見ていきます。授業時間数と教科数やその指導内容量とのバランスで「積載」が「過重」であるか「妥当」であるか、あるいは「適切」であるかが決まります。現在は、「過積載」の状態にあると言われていますが、これまでの授業時間数や教科数などはどうだったのでしょうか。およそ10年ごとに改訂される学習指導要領には、学校で標準として実施すべき授業時間数が示されています。現在のような学校週5日制が完全実施されたのは、2002年。それまでは、土曜日を含めた学校週6日制だったので、学校の年間実施日も総授業時間数も今より多くとることができました。
6日制から5日制と変わったときの小学校第6学年と中学校第3学年の1年間の総授業時間数を比べてみると以下のようになります。
| 1989年 | 1998年 | 2008年 | 2017年 | |
| 小学校 | 1015時間 | 945時間 | 980時間 | 1015時間 |
| 中学校 | 1050時間 | 980時間 | 1015時間 | 1015時間 |
1989年から週5日制が段階的に進められ、1998年には大きく減りました。これは、「少ない内容で子どもが自ら学ぶ力をつけていく、質の高い学びを保証する」といった理屈で学校の教育課程を編成して、授業も改善していくという流れでした。
しかし、1998年の学習指導要領で授業時間数と指導内容を減らしたことが学力低下に結びついたという意見や、これらの時代には新たな学びが必要だという状況認識から、その10年後の2008年、さらに2017年と、小・中学校のいずれも増加していきます。同時に、指導内容も学校週6日制のときと同等に戻り、小学校では中学年の外国語活動や高学年の外国語、小・中学校での道徳が教科として新設されました。
学校で授業実施できる日数や時間が減少しているのに、指導科目や内容が増加し、指導時間もギリギリ取れるところまで設定しなければならないという状態になっています。
カリキュラム・オーバーロードについて考えるときに、科目内容の中に含まれる現代的な教育課題に対応するための新たな学びの増加にも目を向ける必要があります。例えば、GIGAスクール構想でこども1人1台端末の活用環境が整いましたが、そこには情報リテラシー(モラルも含め)教育を更新しながら取り入れていかなければなりません。
地球規模で進められているSDGsに関する内容も各教科の中で扱っていく必要があります。多様性や包摂性、インクルーシブの考え方なども同様です。食育や防災教育、主権者教育など、つまり「○○教育」と言われる内容を、これまでの教科等の学習に加えて指導することが学校教育に求められ、激増している状況にあるのです。限られた時間で多くの内容を扱わなければならない状態では、学習の主体がこどもではなくなり、主体的・対話的で深い学びのある授業の実現は難しくなっています。
社会が大きく変化し、特にAI技術の進展を筆頭に社会のデジタル化と、それに伴うグローバル化が世界の国や地域で一層進む中、学校のカリキュラム・オーバーロードの問題は日本に限ったものではなくなっています。
学校のカリキュラム・オーバーロードは、OECD(経済協力開発機構)加盟国を中心に多くの国や地域で国際的な共通の課題として捉えられています。関係の国や州のカリキュラムの編成の理念や内容などを調査し、「カリキュラムのリ(再)デザイン」と称した「OECD Education 2030プロジェクトが提言する一連のテーマ別報告書」では、カリキュラムの柔軟性と学校の自律的な権限で教科横断的な学びを創り出すことが今後の教育システムに求められると述べています。
つまり、他の国や地域でも、カリキュラム・オーバーロードの問題解決のための効果的な策を模索、あるいは講じているのです。例えばシンガポールでは、「Teach Less, Learn More.(少なく教えて深く学ぶ)」という理念の基にカリキュラムを編成し、同時に教師の質を高め、学校業務への支援も多様に実施する教育政策を進めています。国際的な共通の課題であるカリキュラム・オーバーロードの解決策について、日本のこれからを考えていくためにも他国の取組は参考に値します。
学校教育は、教育目標を実現するために、学習指導要領に基づいてこどもの発達や理解に合わせて、教育内容を学習段階に応じて配列した計画を立てて実施しています。この計画を教育課程と言っていますが、学校現場目線では、これまで話題にしてきたカリキュラムとほぼ同義と捉えてよいでしょう。まさに、「教育課程の過積載」という状態にあります。
教育課程の編成権は校長にあるため、学校の裁量の範囲でカリキュラム・オーバーロードの問題も解決することができる部分もあります。例えば、教科や領域などで扱う内容が重なる場合は、教科横断的な指導計画とすることで、当該内容を扱う時間を調整し、対話する力や課題を追究する力などを重視した指導が可能になります。いわゆるカリキュラム・マネジメントによって、「過積載」状態を解消できるということです。
しかし、そのためには各教科・領域等の内容や指導方法等に精通した教員がいて、学校の実態に応じてマネジメントできる環境が必要です。当然、その時間においてもです。現状では、効果的なカリキュラム・マネジメントが可能な学校はそれほど存在しません。
2027年前後に次の学習指導要領の告示があります。全国小学校長連合会は、国が内容検討の際にぜひ重視してほしいこととして、「小学校教育の充実・改善に関する要望書」を文部科学省に提出しました。そこには、次期学習指導要領の改訂を見越した「指導内容及び指導時数の削減」が記されています。これは、様々な課題を大量に抱えている学校現場の悲鳴を届けようとするものです。
また、次期学習指導要領の内容を左右する答申を審議する中央教育審議会の委員に、全国の小・中・高等学校を代表する校長会の会長が揃って任命されています。このことは、学校現場の実情を国の政策に反映させていくうえで注目すべきことです。
これまでも、学習指導要領の理念と学校現場の実践の乖離という問題が度々指摘されてきました。次代を担うこどもに身につけさせたい力の明確化は必要なことですが、カリキュラム・オーバーロードの状態では、その理念は絵に描いた餅です。それだけでなく、こどもも教師も心身の健康を損ねるような状態に陥ります。
これでは、教育のあり方として本末転倒と言わざるをえません。過去の成果と課題はもちろん、現在の学校現場の窮状を踏まえ、教育活動の最前線に立つ行政や学校、教職員が将来の展望を抱きながら教育活動の展開ができるような国の答申や学習指導要領改訂となることが強く望まれています。