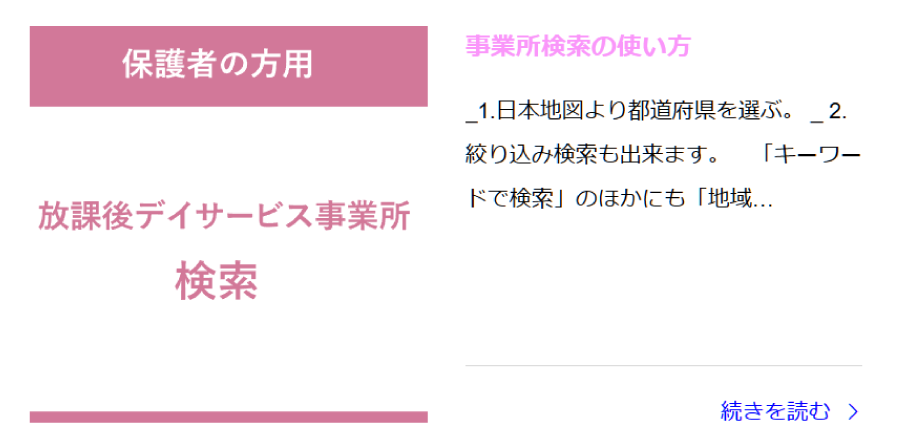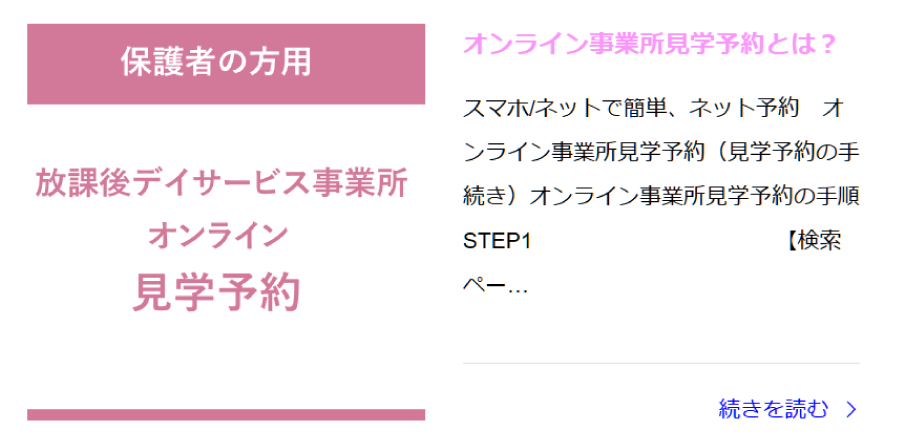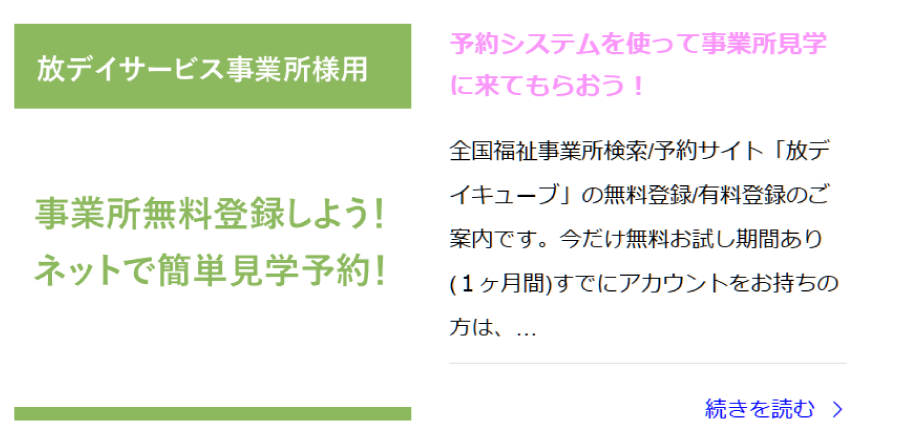みなさんは「気分障害」という言葉をご存知でしょうか? 日常生活、気分がまちまちであるのは普通なことです。名前から判断するに、これを病気とは思わないかもしれません。しかし、「気分障害」とは高揚したり落ち込んだりすることが、普通のレベルを超えて一定期間継続するため立派な病気なのです。以前は「感情障害」と呼ばれていましたが、快不快、喜怒哀楽という感情の病気というより、もう少し長く続く深刻な感情の持続的な病気という意味で「気分障害」と呼ぶようになりました。
「気分障害」と呼ばれるものには、うつ病性障害(うつ病)や双極性障害(躁うつ病)などが該当します。うつ病性障害(うつ病)の特徴は抑うつ状態、双極性障害(躁うつ病)の特徴は躁状態とうつ状態が繰り返されることにあります。ここまで聞けば、ああうつ病や躁うつ病のことを総称して、そう呼ぶのかと思い当たるかもしれません。
以下では、「気分障害」の症状による分類から、仕事を続けるためのコツや接し方のヒントまで説明します。
さて、国際的な診断基準DSM-Ⅳ(アメリカ精神医学会が作成している、精神疾患の診断・統計マニュアルで、精神障害に関する国際的な診断基準の一つ)では、上述のうつ病と双極性障害が同じ「気分障害」のカテゴリーでしたが、最新の診断基準であるDSM-5(2013年)では章の再編成が行われ、うつ病と双極性障害は別々のカテゴリーとして「抑うつ障害群」と「双極性障害および関連障害群」が収録されるようになりました。診断基準のなかでの「気分障害」という枠組みはなくなりましたが、現在でも必要に応じて「気分障害」という言葉は使用される場合があります。
「抑うつ状態」とは、さまざま原因で「気分が落ち込んで何にもする気になれない」「憂鬱な気分」など、心のエネルギーが低下していろいろな精神症状や身体症状がみられることを指します。抑うつ障害群は、機能を妨げるほど重度または継続的にその状態が続くことが特徴だといえます。
抑うつ障害群の種類
具体的な症状により以下のように分類されます。
- うつ病(major depressive disorder)うつ病においては、大うつ病性障害とそれ以外の疾患を分けて捉えています。ここでいう「うつ病」は大うつ病性障害です。
- 持続性抑うつ性障害(気分変調症)
- 他の特定される抑うつ障害、または特定不能の抑うつ障害、また病因により他の医学的疾患による抑うつ障害、物質・医薬品誘発性抑うつ障害、月経前不快気分障害(月経周期に明らかに関連した気分および不安定症状が生じる病態)などがあります。
双極性障害は、躁状態(または軽躁状態)とうつ状態(大うつ病エピソード*)とを反復する精神疾患で、急性期症状から始まり寛解や再発の経過を繰り返します。躁状態とうつ状態が交互に生じることもありますが、多くはいずれか一方が優勢な場合がほとんどです。これが「躁うつ病」と呼ばれているものです。
*精神医学における「エピソード」は、「病相」を意味します。
双極性障害の種類
双極性障害の種類については、躁病や軽躁病、抑うつエピソードの有無や回数などによって定義づけられていますが、あくまでもDSM-5の診断基準に基づき医師が総合的な観点から判断します。
- 双極Ⅰ型障害(躁状態が非常に強く、日常生活に支障をきたすレベルで現れます)
- 双極Ⅱ型障害(軽躁状態と呼ばれる、比較的軽度の躁状態がみられます)
- 気分循環性障害(持続的に気分が不安定で、軽い抑うつや軽い高揚の期間を何回も繰り返します)
また、病因により、他の医学的疾患による双極性障害および関連障害や、物質・医薬品誘発性双極性障害および関連障害、他の特定される双極性障害および関連障害があります。さらに、特定不能の双極性障害および関連障害(明らかな双極性の特徴を示す障害であるが、他の双極性障害の具体的な診断基準を満たさない)もあります。
気分障害のある方が、障害とうまく付き合いながら働くためのポイントには、大きく6つあります。
- 食事と睡眠のリズムを整える
- 残業を避ける
- 調子の上下があることを受け入れる
- 薬の服用を怠らない
- 症状を悪化させにくい仕事を探す
- 休む勇気を持つ
以下、これらの各ポイントについて説明します。
1.食事と睡眠のリズムを整える
気分障害のある方は、躁状態とうつ状態が不定期に訪れるため、体内時計が乱れやすいといわれています。体内時計が乱れると、入眠障害や中途覚醒などの睡眠障害を引き起こしたり、症状を悪化させる可能性が高まります。特に睡眠時間が短くなると「躁状態」を起こしやすくなるといわれています。そのため、決まった時間に「起床」「食事」「就寝」をし、生活のリズムを整えることが重要です。日中は適度な運動や外で活動する機会を設けることで、太陽の光を浴びることも効果的です。
2.残業を避ける
気分障害でうつから躁に転じやすいタイミングとして、繁忙期に遅くまで残業をするなど、過剰に仕事に取り組むことが注意事項として挙げられています。躁状態のときは疲れを感じにくく、自信にあふれているため、無理をしてでも仕事を進めたくなります。しかし、こうした気分の波をできるだけ減らすことが重要なのです。睡眠や食事だけでなく、勤務時間や仕事量も一定の量とリズムを保つようにしてください。
3.調子の上下があることを受け入れる
気分障害のある方にとって、心身の調子の波が日によって変わることは避けては通れない道だといえます。しかしながら、ただ、その波に振り回されるのではなく、焦らずに一歩ずつ克服していくことが重要です。そのためにも、症状が出ている時の状況を振り返り、どのような状況で調子を崩しやすいのか、また同じような状況が起こったときにどのような工夫が可能なのか、後々対処できるようにするため検討するようにしてください。
4.薬の服用を怠らない
気分障害で躁状態になって自信を取り戻すと服薬を怠るケースが多く見られます。しかし、それでは症状が再度悪化し、仕事を続けることが難しくなり、安定的な生活を送ることにも困難が生じます。そのため、定期的に診察を受けて服薬することが、生活を守るためにも必要となります。もし服薬に関して疑問が生じている場合は、自分の判断で服薬を止めずに、主治医に相談すようにしてください。
5.症状を悪化させにくい仕事を探す
気分障害のある方は、以下のような仕事だと安心して長く働けるといわれています。
- 業務量が大きく変わらない
- 勤務時間が大きく変わらない
- 自分のペースでできる
- 他者との共同作業が少ない
「仕事量」と「ストレス負荷」の変化をできるだけ抑えられる事務系の業務であれば、体調の波に合わせて仕事の量を調整しやすくなります。よって、上記のような仕事に就けるよう、会社と相談して配慮してもらうことも見逃せません。
6.休む勇気を持つ
気分障害によって心身の調子が優れない時は、休むようにしてください。無理をしてしまい、状態が悪化するほど、回復にも時間がかかってしまいます。安心して長く働き続けていくためにも、調子が悪い時は勇気をもって休むように心掛けましょう。いざという時の欠勤や休暇をスムーズに取得するために、疾患や特性について上司や周囲に事前に伝えておくことも忘れてはないません。
気分障害は、躁状態とうつ状態を引き起こしたり繰り返したりすることで、仕事や社会的生活に支障をきたすことがあります。
接し方のヒントとしては、気分障害では、感情のコントロールがとれないことで、自分の意志で思うような行動をとれず、自己嫌悪や悲観を繰りかえてしまいます。投薬治療をしながら十分な休養をとり、頑張りすぎないことです。また、うつ病の時はものの見方、考え方が偏ってしまう場合があり、考え方の幅を広げたり、別の角度からみたりすることで気分の改善を図る認知行動療法も有効です。周囲の人は、できる範囲で話をじっくり聞き、アドバイスは専門家に任せるようにしてください。
症状が重い場合は療養のために休職・退職せざるを得ないこともありますが、ある程度回復すれば、疾患と付き合いながら安心して長く働き続けることは可能です。