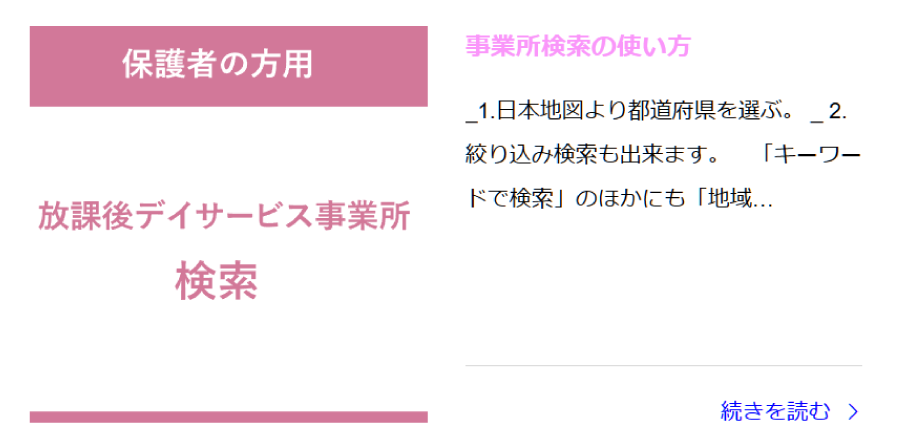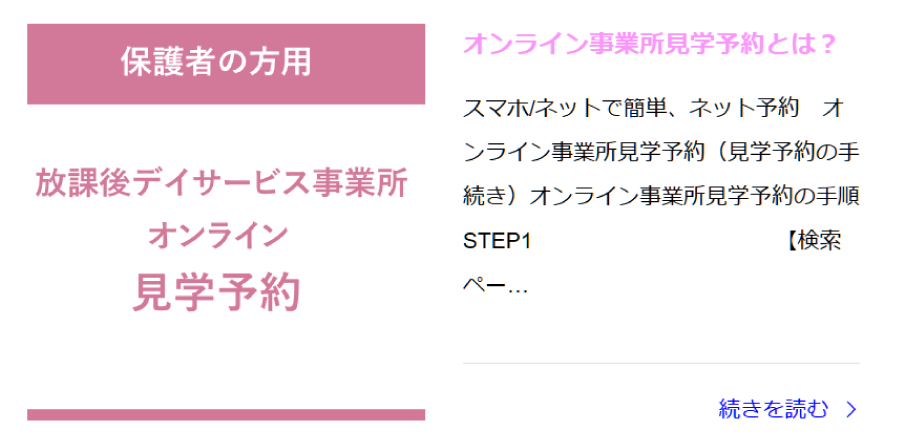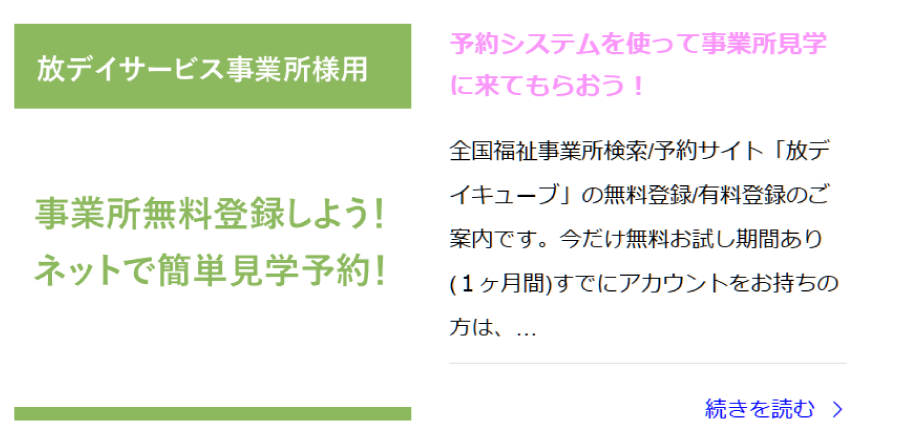吃音は、ほぼ治るとみられていますが、ごくわずかに治らない場合もあるので、その点は用心しなければなりません。では治るとされる多くの吃音は、どのような治癒過程を経て完治するのでしょうか? またごくわずかと言われる治らない吃音は、どのようなことがその要因と考えられるのでしょうか? 以下ではそれらのことを説明してみたいと思います。
幼児の自然治癒
幼少期からの発達性吃音は、こども100人に対して5人が発症します。研究報告により違いはありますが、発症した吃音が回復する確率は、最大で約80%程とみられています。つまり、こどもが100人いたら5人が吃音を発症し、その後4人は治癒し、1人は成人以降も症状が残るということになります。
アメリカの吃音研究者ヤイリ博士らの報告によると、回復した子としなかった子の相違点は以下の点がみられると言います。
【幼少期に吃音が回復しやすい条件】
- 女児である。
- 発症年齢が低い。
- 吃音のある親族がいない。または、いても回復している。
- 言語スキルが高い。
- 非言語の知能検査の得点が高い。
吃音の自然治癒を妨げる要因
吃音の自然治癒に関して、本人の持つ気質(過敏さや、感情表出の抑制)が吃音の自然な改善を妨げ、吃音を維持させることに関わっているのではないかと考える研究者もいます。
また、遺伝的要因ではいくつかの遺伝子が吃音を維持させることに関わっているとも言われています。
完治してはいないけど、以前より随分軽くなったという人もいます。この場合も過程は様々ですが、例えば「以前は人前で音読ができなかったが、今はできるようになった」というように日常で困ることが少なくなっています。要因はいろいろ考えられますが、「言えた!」という成功体験を積むことにより、特定の場面を乗り越えていくことが多いようです。
日常に適合していくケース
自己流で、話し方や様々な工夫をしている場合などは、ごまかしながらも日常生活の中で適合していっているようにみられます。
こどもの頃に発症した吃音の症状が出る頻度が減っていったり、ストレスなどの影響をあまり受けなかったりすると、日常生活において吃音の支障をほとんど受けないこともあります。また、どもらないように言葉の言い換えをしたり、余計な音の挿入(例えば、えーっと、あのー、などを付けて話し始める)をしたりするのは、吃音が治っているのではなく、どもらないよう工夫をしているということになります。どもらないための工夫をしていくうちに、日常生活で適合していくことによって吃音の悩みが減っていくことがあります。
何かのきっかけで再び悩むケース
工夫をしてなんとかやり過ごし、いつの間にか吃音が軽くなっていった人の中には、何らかのきっかけにより再び吃音の悩みが深くなることもあります。例えば、小さい頃から吃音があっても生活に支障なく過ごしていた人が、就職活動や仕事の何らかのきっかけに、名前や決まった言葉が言えないという悩みが再び始まることがあったりします。
適切なセラピーを受けることで吃音が治る人がいます。実は、どもりがあってもセラピーを受ける人の割合は、実際には低いというのが現状です。セラピーを受ける人が少ないのには、様々な理由があります。吃音は日常になんとか適合できることが多いことや、吃音は治らないと思っている人も多くいます。また、吃音を診ている病院が少ないことや費用が高いなど様々な理由も考えられます。
セラピーを受けて良くなる人の場合には、以下のように様々な回復例があります。
テクニックを身につける
テクニックを身につけて、実際の場面で使うことができるようになることが大事です。いつもなら吃音が出てしまう場面や苦手な言葉を「自分でコントロールして言える」ことにより、自信が生まれます。自信が生まれることにより、日頃抱えていた不安が減少します。そして、いつの間にか吃音のことをあまり考えなくなり、上手に吃音をコントロールし続けることが自然になっていくのです。この場合、治ったというよりも、良い状態を自己管理できるようになっているという方が適切なようです。
《事例:言語聴覚士から治らないと言われ、どもり続けた男性》
この男性は思春期になってから症状が出始めて、すぐに病院に行きました。病院では言語聴覚士から「吃音は治らない」と言われ、ゆっくり話す練習を数回行っただけで、効果もないまま「吃音は治らない」と思ってあきらめていました。
しかし、仕事で支障をきたすようになり、別の診療所に行くことにしました。この方は吃音について否定的な考え方を持っていないことを話されました。どもってもそんなに恥ずかしさはないけれども、どもることが不便で仕方ないので、楽な話し方を練習することになりました。そこで、言葉が楽に発せられるよう発声練習を行うことにしました。どもる時の発声と楽に話せる発声を比べてもらい、徹して発声練習を行ったところ、短期で改善が見られました。
心理的なアプローチを行う場合は、どもっても良いという考えを育てながら、様々な工夫を止めていくことが重要です。そして、本来自分が持っている自然な話し方を引き出すために、心理療法に基づいた取り組みを行います。取り組みがうまくいくと、吃音への否定的な考えが軽減され、吃音症状自体も減っていきます。また、取り組みは一人ひとりの吃音に合わせて行う必要があり、自分に合った方法、結果の出る方法を用いることが有効であるのは言うまでもありません。
吃音への考え方が変わることによって、話しやすさが出てくる
吃音への否定観が薄れていくことで、話しやすさが出る人がいます。また、他人からの評価を気にするあまりに、自分のペースで話せない人がいます。そのために言語訓練に加え、認知行動療法や、その他の心理療法が用いられることがあります。
個人差はありますが、吃音がある人は、否定的な考えを持つ傾向があります。楽に話せない苦悩が続くと、「自分は、周りの人が当たり前にできることができない」と考えてしまうこともあります。そのため、自分の持っている能力や、自分自身の存在についても否定的に考え、「吃音があるから自信がない」という人もいます。
吃音観(吃音のことをどう捉えるか)は、人それぞれです。環境や時期によっても変るかもしれません。また、吃音観が変わることで吃音のことをあまり気にしなくなったり、吃音症状をコントロールしやすくなる人もいます。当事者を苦しめている「思考のサイクル」を変えていくことは、楽に話すためには有効だといえす。
吃音治療を受けても良くならなかった理由として考えられること
セラピーがうまくいかずに、吃音が良くならない場合もあります。一生懸命取り組んだけれども結果が出なかった場合もあるでしょう。これらは、取り組んだ方法が合っていなかったことや、改善を阻止するような何らかの課題がある場合なども含め、本人の努力では難しいとされる様々な要因が考えられます。例えば、他の精神疾患なども、吃音の改善が進まない理由として考えられるからです。
当り前なことですが、吃音は人によって症状も程度も異なります。そのため全ての吃音のある人に効く方法などあるはずはないのです。そして、一つ一つのセラピーも取り組んだ人が100%吃音が良くなるわけではありません。
セラピストのレベルも様々です。当事者の課題だけではなく、セラピーを行う側の要因も多々あります。言葉の矯正だけに重きを置く古典的な吃音セラピーもいれば、マニュアルに頼りすぎるセラピー(個々の当事者に適応していない)などは、良くならなかった理由の一つかもしれません。
このような現状において吃音治療には、「楽に話せること」と「吃音への否定観をいかに乗り越えていくか」がポイントとなるのではないでしょうか。世界的に有名な吃音研究者ヴァン・ライパーは、「どもることを恐れ続ける人は、どんなセラピーを受けてもうまくいかないであろう」と述べています。この「吃音への恐怖」をいかに手放せるようになるかが、改善への重要なポイントだと言えます。
様々な課題を抱えて
吃音がある人は、社交不安障害や他の心理的な課題、親子関係や不登校など、吃音だけではなく様々な問題を同時に抱えていることもありえます。これらの複雑な課題が、吃音治療が困難な要因となっている場合もあります。いずれにしても、セラピーがうまくいかない理由は、一概にはわかりません。
ただ、「大人になってからの吃音を改善された方々がたくさんいる」という事実を知っていただけたら幸いです。あなたがもし吃音の改善に興味を持たれたら、まずは自分の吃音を知ることから始めてみてはいかがでしょうか?
幼少期からの発達性吃音は、幼少期に回復することが多いです。中学生以降、吃音が続く場合には、日常生活になんとか適合して軽くなっていく人と、セラピーなどを受けて回復していく人がいます。
回復過程は様々であり、個人によって違います。また、治療を受けても良くなる人と良くならない人の違いは多様であり、一概に言い切ることはできません。しかし、回復の重要なヒントとして《「吃音への恐怖」をいかに手放せるようになるか》にあることは、記憶に留めておいてよいことだと言えるでしょう。