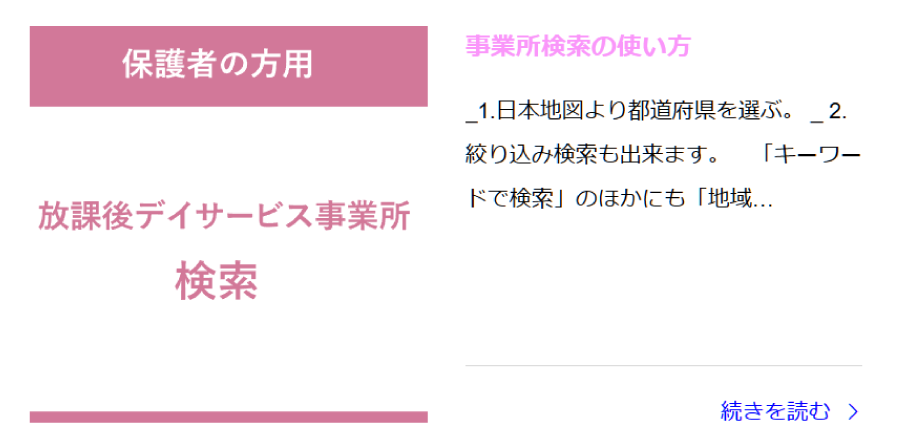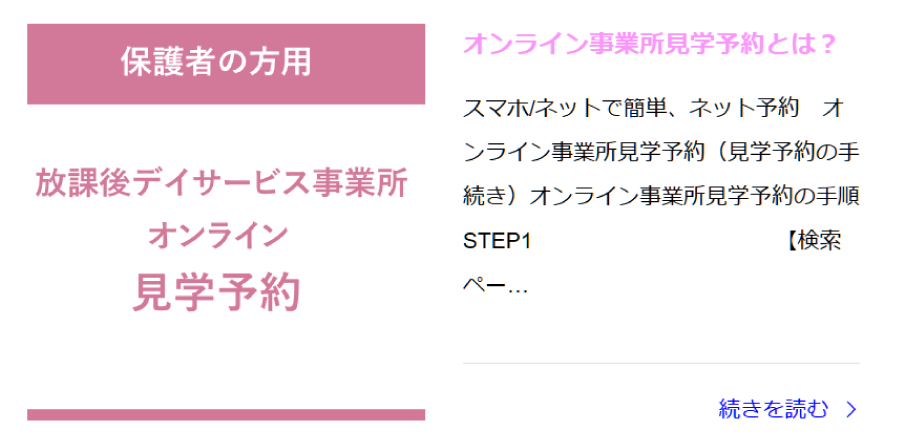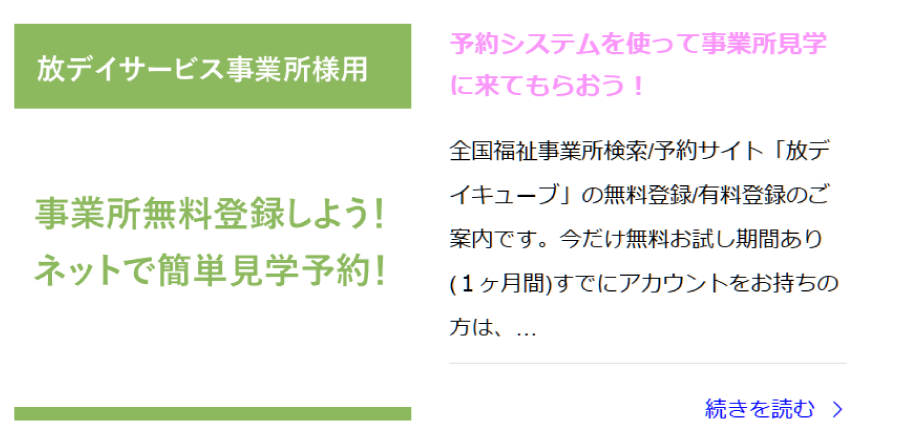障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして、令和7年10月から就労選択支援が開始されます。
就労選択支援については、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。特別支援学校高等部、高等学校、中等教育学校の後期課程(以下「特別支援学校等」という)に在籍する生徒の利用も見込まれます。保護者の方や就労移行支援事業所、並びに就労継続支援B型事業所の方には、特別支援学校等に以下のような通達がされていることを知っておくことは、有意義だと思われます。令和7年10月からの障害者の新たな就労方法となる就労選択支援の概要や、特別支援学校等に在籍する生徒の就労選択支援の利用に関する留意点等については、下記の通りです。
(1) 就労選択支援の趣旨
就労選択支援は、令和7年10月1日より開始する新たな障害福祉サービスであり、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することを趣旨とするものです。
具体的には、専門的な研修を修了した支援員が、本人と協同しながらアセスメントを実施し、多機関連携によるケース会議や地域の情報収集等を行った上で、本人の特性や意向等に応じた就労の選択を支援するもので、就労選択支援の利用は、本人の自己決定の尊重および意思決定の支援につながるものと考えられます。
(2) 就労選択支援の具体的な内容
- ① 基本的なプロセス
- 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識および能力の評価、並びに就労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。
- アセスメント結果の作成に当たり、利用者および関係機関の担当者等を招集して、多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等から意見聴取を実施。
- アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
- 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
——–
- ② 作業場面を活用した状況把握(アセスメント)について
就労選択支援では、作業場面を活用した状況把握(アセスメント)として、障害の種類および程度、就労に関する意向および経験、就労するために必要な配慮および支援、適切な作業の環境等の項目を把握する。その際、同様のアセスメントが既に実施されている場合は、必要に応じて、当該アセスメントを活用することができる。なお、新たな情報が必要な場合は、就労選択支援事業者が追加的に実施する。
——- - ③ 多機関連携によるケース会議について
就労選択支援では、就労選択支援利用後の適切な支援につなげていくため、地域の関係機関が集まり、利用者が希望する就労に向けた支援の方向性等について検討する。
(3) 就労選択支援の対象者
就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者、および現に就労移行支援または就労継続支援を利用している者を対象とする。
なお、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となることから、就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用する必要がある。(なお、50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。)
ただし、
- 近隣に就労選択支援事業者がない場合
- 利用可能な就労選択支援事業者数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
は、就労移行支援事業者等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用を認めることとしている。
なお、令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われている者が対象となる予定であるが、令和9年4月以降の取扱いについては改めてお知らせをする。
(4) 就労選択支援の支給決定期間及び実施期間
支給決定期間は原則1か月間とする。
支給決定期間のうち、作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)は、2週間程度を想定しているが、個々の状況に応じて、5日間程度の短期間での実施も可能とする。
(5) 就労選択支援の実施時期
就労選択支援は18歳以上の障害者向けの障害福祉サービスですが、特別支援学校等に在籍する生徒に対して、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校等の1年次から利用可能であり、また、在学中に複数回実施することも可能としている。
なお、15歳以上18歳未満の生徒が就労選択支援を利用する場合は、児童相談所長が障害福祉サービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知することが必要です。
(1) 就労選択支援の趣旨や意義に関する周知
本来、就労支援は、生徒本人の意向や適性、就労能力等に関するアセスメント結果を踏まえたサービスを提供するものです。
就労選択支援は、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものであり、特別支援学校等におけるキャリア教育・進路指導においてもその結果を活用することができます。
そのため、令和7年10月以降、特別支援学校等の卒業後に就労系障害福祉サービスを利用して、一般就労に向けた訓練を行う意向がある場合には、就労選択支援によるアセスメント結果を踏まえた上で、一般就労に向けた目標設定や就労系障害福祉サービスを利用した訓練の実施等、生徒本人が進路を検討するための情報を得た上で方向性を決めていくことが重要です。
このような本制度の趣旨や意義を踏まえ、特別支援学校等においては、自治体担当者や相談支援事業者等と連携し、本制度について生徒や保護者への周知に協力いただくとともに、生徒が就労選択支援の利用を希望する場合には、自治体や相談支援事業者を案内するなど、理解と配慮をお願いします。なお、生徒や保護者に情報提供を行うに当たっては、別添のリーフレットもご活用ください(別添3参照)。
(2)地域における就労選択支援に係る連携体制
就労選択支援の利用時期に定めはないが、例えば、夏期休業中に就労選択支援のアセスメントの実施希望が集中し、就労選択支援事業者が受け入れ困難となる場合も考えられることから、各自治体と教育委員会、特別支援学校等が連携を図り、各地域における就労選択支援に係る連携体制の構築に協力してください。
(3) 特別支援学校等と就労選択支援事業者等の連携
特別支援学校等に在籍する生徒が就労選択支援を利用する場合に、適切かつ効果的にアセスメント等が実施され、生徒の進路選択に有効に活用されるよう、特別支援学校等と就労選択支援事業者等が連携を図るとともに、本人や保護者への同意を得た上で、特別支援学校等における個別の教育支援計画を共有するなど、就労選択支援事業者に対する情報提供について協力してください。
また、生徒の学習の状況等を把握している特別支援学校等に対して、就労選択支援事業者からケース会議への参加が求められる場合もあることから、必要に応じて協力してください。
(4) 特別支援学校等における実習等の場面を活用した作業観察の実施
就労選択支援のアセスメントにおける作業観察については、特別支援学校等に在籍する生徒が就労選択支援事業所に通所して行う作業を観察する場合のほか、特別支援学校等の教育課程に位置付けられた校内実習や作業現場等における実習等の場面に就労選択支援事業者が出向いて、当該作業の観察を行うことも可能です。このため、就労選択支援事業者から、アセスメントにおける作業観察の場面として、特別支援学校等における実習等を活用することについて依頼があった場合には、可能な限り協力してください。
なお、この場合、特別支援学校等の教育課程に位置付けられた各教科・科目等の目標・内容に沿った実習等を作業観察の場面として活用するものであり、生徒は学校の授業に出席しつつ、同時に障害福祉サービスを利用する形となります。
(5) 就労選択支援を利用する場合の特別支援学校等の出欠の取扱い
特別支援学校等に在籍する生徒が就労選択支援事業所に通所して就労選択支援を利用する場合、長期休業期間中に通所する場合と、特別支援学校等の授業日に通所する場合とが想定されます。
生徒が学校の授業日に就労選択支援を受けるために登校できない日については、当該生徒の出欠の扱いについて、校長の判断により「選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌引等の日数」に計上することが可能です。
また、校長の判断によって、就労選択支援を学校の教育活動に位置付け、出席として扱うことを妨げるものではありませんが、その場合には、就労選択支援における生徒の活動が、学校の教育課程における目標・内容に沿うものであることを確認した上で、出席として扱う必要があります。
教育関係機関および福祉関係機関におかれては、就労選択支援の施行後、1(3)のとおり近隣に就労選択支援事業者がない場合等において、特別支援学校等に在籍する生徒が、就労移行支援事業所等による従来の就労アセスメントを利用する際には、平成29年4月25日付け事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」の2、4、5で示す内容を踏まえて、従前どおり引き続き適切に対応してください。(別添4参照)
なお、別添4の事務連絡においては、就労継続支援B型の利用対象について、「特別支援学校在学者が卒業後すぐに利用する場合には、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者を対象としている」旨を示していますが、就労選択支援の施行後においては、近隣に就労選択支援事業者がない場合等においてのみ、就労移行支援事業所等による従来の就労アセスメントを経た利用が認められることに留意してください。
また、従来の就労アセスメントの実施方法やアセスメント結果の活用方法についてとりまとめた「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」を別添のとおり改訂したため、参照してください。(別添5参照)
(添付資料)
別添1 令和7年3月31日付け障障発0331第3号「就労選択支援の実施について」
別添2 令和7年4月21日付け事務連絡「「就労選択支援実施マニュアル」の送付について」
別添3 就労選択支援に関する案内用リーフレット
別添4 平成29年4月25日付け事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」
別添5 各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル(令和7年5月改訂)