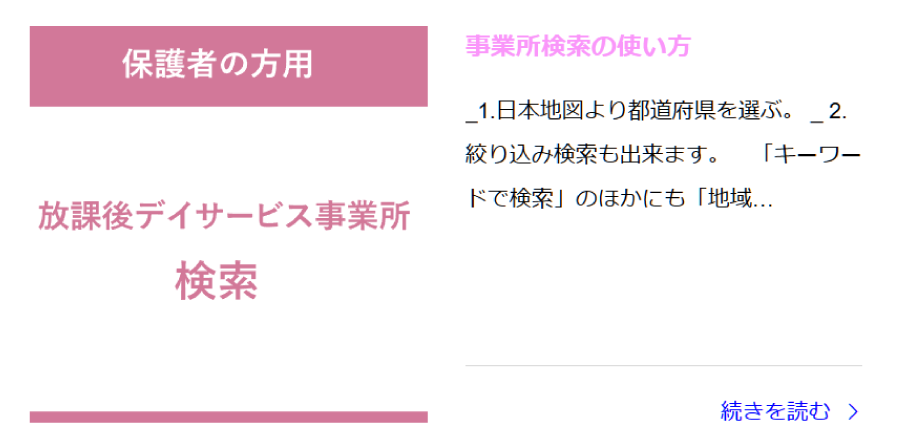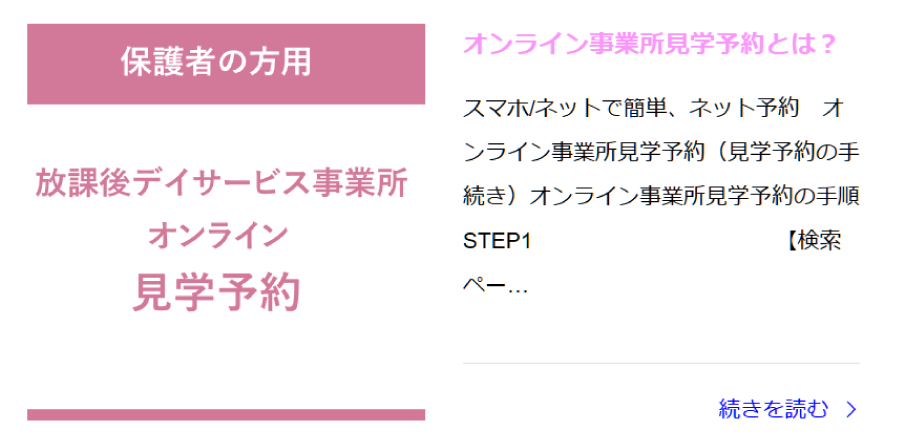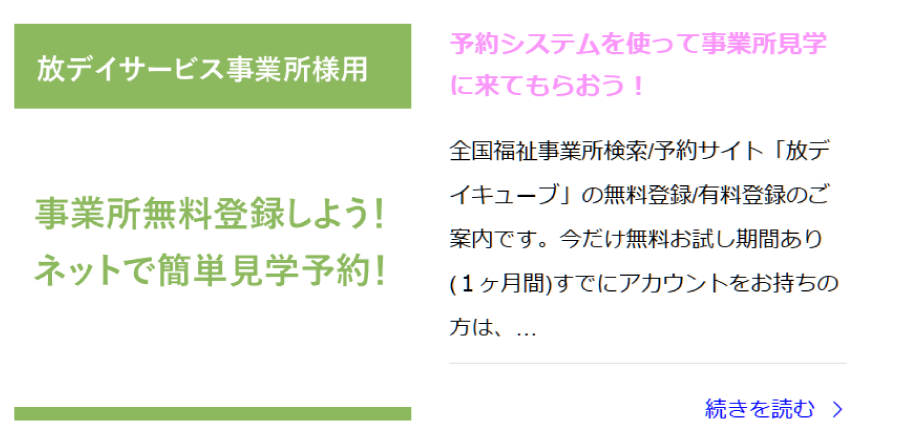言葉というものは、目に見えるものではなく、発した後にはすぐに消えてしまうように思われがちなものです。しかし、なにげなく発した言葉が、受け手にとっていつまでも消えぬ言葉であったりします。それは良い意味でその人を勇気づける言葉であったり、悪い意味でその人を傷つける言葉でもあります。これらのことは当たり前のように、誰でも経験上知っていることです。以上のことは、立ち止まる余裕のある時にこそ、当たり前にいえることであって、忙しい時などは、ともすると人は目に見えず、言葉のように消えてしまいやすいものには意識が向きにくい傾向があります。そのため、日頃のストレスから暴言を吐いても罪悪感を感じにくく、感覚が麻痺してしまうと無自覚・無意識的に暴言を吐いてしまうケースがあります。だからこそ、施設職員は自分たちが発する言葉や表現に常に意識を向けて仕事に取り組む必要があります。
虐待は、身体的な外傷ですぐに判明する暴力が全てではありません。厚生労働省の定める虐待防止法では、以下の5種類が虐待として分類しています。
| 虐待の種類 | 内容 |
| 身体的虐待 | 暴力的行為によって傷やあざ等の外傷や痛みを与える行為。 外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 |
| 心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言葉や態度、無視や嫌がらせなどにより精神的苦痛を あたえること。 |
| 性的虐待 | 本人が同意していない性的行為やその強要 |
| 経済的虐待 | 本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を 強制的に制限すること。 |
| 介護放棄 (ネグレクト) |
必要な介護サービスの利用を妨げ、世話を放棄すること。 高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること。 |
このように、身体に関わる行為だけでなく、「言葉の暴力」で精神的なダメージを与え、尊厳を傷つける行為も虐待とされています。
「スピーチロック」とは、言葉の拘束と呼ばれています。「ちょっと待って!」「ダメ!」という言葉で相手に身体的・精神的な抑制を行うことです。スピーチロックは一般的な声かけと明確な差がないため、分かりにくいのが特徴ですが、虐待と共に問題意識が高まっています。
例えば…
- 利用者から「トイレに行きたい」「部屋に戻りたい」と言われた。
- 施設職員が別の利用者の対応に追われており、「ちょっと待って!」と返した。
このような声かけはスピーチロックに該当します。つまりスピーチロックとは、言葉により利用者の行動を制限することです。またスピーチロックは「行動意欲の減退」「行動抑制によるADL低下」「ストレスによる認知症状の悪化」などにつながる可能性があるため注意しましょう。
スピーチロックが起こる原因は「人手が足りない」「複数の利用者の対応が重なる」「事故防止の意識のため」などがあげられます。
例えば、介護現場の下記のような状況はどうでしょうか。
- 転倒リスクがある利用者の歩行に付き添っている
- 別の転倒のリスクがある方が立とうとしている
- その場には自分だけ
この場合、事故防止のためとっさに「座ってて!」「動かないで!」など、スピーチロックとなる言葉が出てしまうケースがあります。
このような状況が起こる前に「職場環境の調整」「業務整理」などに取り組んだほうが良いでしょう。
また、すぐに対応できない場合は「〜していただけますか」と、利用者の判断を促すような優しい口調や、具体的な内容を伝えることが大切です。
職員が利用者に投げる「言葉の暴力」とは具体的にはどのようなものでしょうか?
施設で実際に起きた言葉の暴力の一例は以下の通りです。
- 職員が利用者に「あほ」「ばか」「忙しいねん」と暴言を吐いた。
- 難聴の利用者に「うるさい」とペーパータオルに書いて渡した。
このような言動は決して許されるものではありません。しかし、なぜ、このような言葉を吐いたのでしょうか。背景には、多忙を極める現場でのストレスにより言葉遣いが乱れているという事実もあるのでしょう。今一度、自身の言葉遣いについて再確認し、利用者への態度を改める必要があります。
スピーチロックの対策として「工夫した言葉がけ」があげられます。下記に介護現場でよくあるスピーチロックと、その言い換え例を記載します。
| スピーチロック例 | 言い換え |
| ちょっと待ってください! | あと○分で行きますね。 |
| あちらに行ってください! | あちらの席が空いていますよ。 |
| 危ないから動かないで! | どうされましたか。 何か気になることがありますか。 |
| まだ座ってて! | こちらに座りませんか。 |
| だめです・やめてください! | どうされましたか。 |
| まだ寝ててください! | ○時に起こしますから大丈夫ですよ。 |
上記のような言い換えで言葉の印象は大きく変わります。
また、「すみませんが、〇〇しませんか」「よければ、〇〇しましょう」など、クッション言葉を使うと柔らかいニュアンスで伝わりやすくなります。
現場でよく見かける言葉の乱れには以下のようなものがあります。
- 利用者に対して、敬語を省略した「ため口」を使い、上から目線で話しかけている
- 利用者に小さなこどものような「赤ちゃん言葉」で話しかけている
- 利用者に「ちゃん付け」や「あだ名」で呼びかけている
これらの言動は、職員に悪気はなく、利用者との関係を深めるために使用しているというケースが多いです。しかし、これらの言葉は人生の先輩に対して使うものではありません。職員は常日頃行っている自身の言動について、リスクマネジメントの対象として位置付けておくことが大切です。また、避けたい表現や言葉として、「~してね」「ダメでしょ」「危ないから座ってて」というようなものも挙げられます。「~していただけますか?」「いつでもおっしゃってください」「すぐに行きます」というような言葉に改善が必要です。
言葉の暴力は職員から利用者へだけでなく、職員間でも生じます。職員間での言葉の暴力は、外傷のように目に見える被害がない分、「これっていじめ?」「仕事だから仕方ないのか?」と自分では判断しにくい場合が多いです。しかし、職員間の言葉の暴力はパワハラ、セクハラ、マタハラなど、社会で問題視されている「ハラスメント」に該当します。言葉の暴力は直属の上司や職場の人事、社外の相談窓口に相談してください。
職員間での言葉の暴力には「暴言」「嫌み」「陰口」があります。具体的な内容に関しては以下の通りです。
- 書類を提出すると「やり直せ!」と怒鳴られ、正当な理由なく何度も書類を突き返される
- 同僚の前で「馬鹿だな」「無能だ」と暴言を浴びせられる
- 仕事で成果を出すと「無資格のくせに生意気」と嫌みを言われる
- 妊娠中の時短勤務で「周りの迷惑を考えていない」「脳天気」と陰口を言われる
- 「女のくせに」「女には無理だ」と仕事を任せてもらえない
施設職員の言葉の暴力や虐待が減らない理由として、溜め込んだストレスのはけ口として立場の弱い障害者や新人に八つ当たりしてしまうことが多いようです。そして、知識や技術不足で、うまく対応できないストレスで障害者に八つ当たりしてしまうケースも考えられます。人員不足が深刻化している施設現場で被虐障害者の言動により、職員への負担が多いことが言葉の暴力や虐待を招く要因とされています。
例えば介護職の場合、多くの介護職員は「高齢者のよりよい生活をサポートしたい」という熱意で仕事に取り組んでいますが、言葉の暴力を発してしまう介護職員がいるのも事実です。厚生労働省の調べでは、介護施設で虐待が起こる要因について以下のように報告しています。
- 教育、知識、介護技術等に関する問題
- 職員のストレスや感情コントロールの問題
- 虐待を助長する組織風士や職員間の関係の悪さ、管理体制等
- 人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ
言葉の暴力は、相手にどのような影響を与えるのでしょうか。下記に具体的な例をあげてみました。
- 利用者の意欲・活気がなくなる
- 家族の不信感につながる
- ケアの拒否につながる
- 身体的・性的などほかの虐待につながる
日常的に言葉の暴力を受けると、利用者は自信をなくし意欲・活気を失います。本人の様子の変化は、家族の不信感につながります。また、認知症により「言葉の内容」を忘れたとしても「嫌なことをいわれた」という感情は残ります。結果として「暴言をはかれた相手のケアを拒否する」「その人といるときは不穏になる」などにつながります。利用者へ言葉の暴力を浴びせることがきっかけで、虐待が常態化し身体的虐待や、性的虐待に発展していくケースもあります。
例えば、
- 利用者本人が認知症のため言葉の暴力を訴えることが難しい。
- 職員が利用者に対し、言葉の暴力をしているのを目撃してしまった。
そんな利用者のご家族や別の職員が言葉の暴力を報告・相談するべき先は以下の通りです。
①該当職員を含めて施設運営者と話し合う
利用者への言葉の暴力を目撃したご家族や職員は、まず該当職員を交えて施設運営者と話し合い、事実確認を行いましょう。
②警察に相談する
利用者の居室にカメラやレコーダーを設置し、虐待と認められる暴言の証拠を用意し、警察に相談してください。言葉の暴力は立派な犯罪行為です。
③弁護士に相談する
言葉の暴力を目撃しても、警察に相談できるような証拠がなく、施設運営者が話し合いに応じない場合は弁護士への相談が適切です。
職員間での言葉の暴力やハラスメントに悩み、自力での解決が難しい場合は、以下のような証拠を用意してください。
- 暴言や悪口の記録やメモ
- 客観的な第三者による証言
- メール、SNSの文章
- 医師による診断書
職員間での言葉の暴力での相談先は、以下の通りです。
- 直属の上司
- 会社の上層部
- 労働局、労働基準監督署
- 社外の相談窓口
労働局や労働基準監督署に相談した場合、相談員が会社に連絡し、事実確認や指導を行います。しかし、事実確認に時間がかかるケースが多く、暴行などの刑法に結びつかない場合、責任の追及が難しいことがあります。自身が受けているハラスメントが違法行為に該当するか、事前に調べることをオススメします。また、職場のハラスメントに関する公的な相談先は労働局以外にも様々です。
- 労働委員会や都道府県庁労政主管課
- 全国の法テラス地方事務所
- 法務局
- 法務大臣の認証を受け、「かいけつサポート」を行っている民間事業者
これらの相談先は、職場でのハラスメントを直接解決できません。まずは上記の相談先で、解決に役立つ法制度を教えてもらってから上司や人事、労働局などに相談するという方法もあります。
現場の「言葉の暴力」は、放っておいて解決できるものではありません。ここからは言葉の暴力への3つの対応をご紹介します。
①普段の言葉遣いの注視
言葉の暴力を未然に防ぐには、接遇や言葉遣いの教育が重要です。心理的虐待の原因は「個人の人格の問題」ではなく、「正しい対応を知らない」「利用者への理解がない」など知識不足・教育不足から起こるケースが多いようです。また、言葉の暴力は、日々の言葉の乱れから起こります。
- 上から目線で利用者に話しかける
- タメ口・赤ちゃん言葉で話す
- 「ちゃん付け」「あだ名」で利用者を呼ぶ
上記は基本的に目上の相手に使う言葉ではありません。利用者の尊厳などを考慮し、こうした倫理観や、日々の言葉遣いなどを注視するのも重要です。
②職員がひとり問題を抱え込まない環境作り
言葉の暴力は、職場環境によっても起こります。防止策として相談しやすい雰囲気作りは大切です。過去に茨城県の介護施設で発生した心理的虐待の事例がありました。その施設の職員から虐待の要因として下記の意見が聴取されました。
- 「職員同士の話し合いの機会がない。」
- 「マニュアルがどこにあるのかわからない。」
- 「だれに報告することになっているか、よくわからない。」
言葉の暴力は職員ひとりの責任ではなく、こうした職場環境の問題でもあります。
「職員のストレスコントロールのために相談しやすい雰囲気作り」や「対応が難しい利用者の対応の共有」など、誰かひとりが問題を抱え込まないような環境作りを意識してみてください。
③人員配置の工夫による多忙の解消
業務改善や、適切な人員配置による忙しさの解消も、言葉の暴力による心理的虐待の予防法です。厚生労働省の調査で虐待の要因としてあげられているのは、「人員不足や人員配置の問題および関連する多忙さ」があるとしています。ほかの要因と比べて全体に占める割合は少ないのですが、業務改善による職員の負担軽減は大切だといえるでしょう。各現場で実情は異なります。まずは、業務改善のためには「現状の課題の把握」「改善計画の立案・実行」「計画の振り返り」などを行ってみてください。
施設職員が日々の業務の研鑽に励むことで、サービスの質は向上します。しかし、その一方で利用者との距離感が妙に近くなったりしてしまいます。業務に対する慣れから態度が横柄になってしまうという難点も生じやすくなります。長年培った職務での経験で感覚が麻痺してしまうことのないように、専門職として自分自身の使っている言葉や態度を見直す機会を定期的に設ける必要があります。